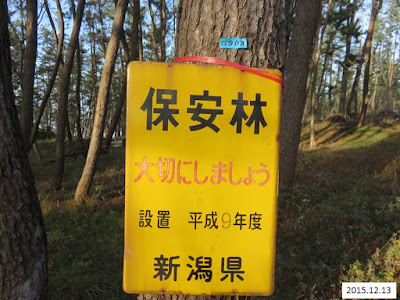有人ヘリコプターによる薬剤散布が実施された松林として、胎内川に近い方は2反復区(計178本)、中央部(株式会社日立産機システム中条事業所の国道135号線を挟んで前辺り)で2反復区(計207本)、薬剤無散布(コントロール)松林として国道135号線の反対側の裏山で2反復区(計127本)を調査対象にしました。薬剤散布が実施された松林の中央部は、胸高直径が太く樹高が高いマツが多数残っている林分でした。
散布区の古い枯れは13本だったのに対して、無散布区の古い枯れは116本もあり、枯れても放置された割合が高いことを示していました。散布区では当年枯れと判断された新しい枯れはわずか2本だけで、無散布区の12本に比べて著しく低い枯死率でした。薬剤散布をせずに放置された松林は、毎年の松くい虫被害で残っているマツの本数そのものも非常に少なくなっていますが、強風時に枯死木が途中で折れたり倒れたりして危険な状態でした。
いずれデータをいろいろな角度から詳しく解析してみるつもりですが、枯死木や伐倒木とその根株などにドリルで穴を開けて材片を採取してきましたので、DNA診断でマツノザイセンチュウの寄生の有無も調査するつもりです。
薬剤の残効性を考慮してヘリコプターで適期に必要回数(マイクロカプセル剤は年1回、乳剤や液剤は年2回)予防散布をし、散布をしない林縁部は殺線虫剤の樹幹注入をし、枯れた木は伐倒駆除するという基本対策を実施すれば、松くい虫被害は僅少に抑えられることが明らかです。三保の松原で見られた、根系癒合によるマツノザイセンチュウの隣接木への移動・感染がここの松林でどれくらいあるかは不明です。
胎内川では産卵の終わったサケ(鮭)を狙って釣りをしている人がいましたが、東の方向には奥中条(なかじょう)の山々と、さらにその奥に福島県のすでに雪が積もっている高い山脈が見えました。肥料工場の裏の砂山では、5年間の契約で信越建設工業株式会社による山砂採取が行われていました。
計画した調査が終わって、計画通り午後5時に新潟駅でレンタカーを返却して、自宅に戻ったのは夜の8時半頃でした。棘(とげ)のあるタラの木や茨(いばら)の生えている林床を歩き回ったので棘に引っ掻かれた足は少しヒリヒリしますが、思い切って調査をしてきたお蔭で現場の今年の状況が把握できました。勤務が休みの日曜に一日中調査を手伝ってくれた私の研究室の卒業生の孫 立倉博士に感謝です。